先日、投稿した、秋田の少子化対策や両立支援などをテーマに、とある原稿でボツになったほうの記事。
これからの日本の状況を考えると、うちの息子も、産まれながらに高度成長期を過ごした人とは違った重い課題を背負うことが想像され、試練に挑戦する使命を与えられているように思います。
試練もおもしろがるぐらいに、タフな精神力に育って欲しいなぁ・・・と願うのでした。
以下、転載。
*****
少子高齢化、人口減少社会により、既に様々な影響が出始めています。
子供の数がどんどん減っていますが、なぜ子供の数を増やしたいのでしょう?
社会保障制度等に不安が生じるため?
少子化が改善したら様々な問題が解決され秋田はよくなる?
確かに少子化対策は大事でしょうけど、それだけだと片手落ちの政策です。
ニート、フリーター、心の病の増加、国際競争力の低下・・・
世の中の若者を見ると、果たして現状の方向性のまま子供が増えたところで、日本の将来像がどうなっているか想像すると・・・
自立できない若者が増えたところで、社会保障制度等の問題は改善しないでしょう。
様々な問題の解決は、頼もしい若者達が育っている前提での話しになるはずです。
まずは、しっかりとした未来のゴールを描いてみる。
秋田はどんな方向を目指すのか・・・
小国寡民・・・。古代の賢人・老子は、「柔弱」「謙虚」「寛容」「知足」を生き方の指針、四徳とし、住民が少ない小さな国を理想としました。現代のブータンは鎖国に近い体制で老子の理想とした国に似ているように思います。
しかし賢人・孔子の、「人間は獣の生活には戻れない、人間社会を離れて、いったい誰と暮らせというのか」という言葉の通り、世俗を捨てた生き方というのも難しいです。
今後の秋田の在り方を考える上で、度々話題に出るブータン以外に、興味深い民族がいます。ユダヤ人です。ユダヤ人の天才出現率の高さは驚異的で、その秘密は家庭を中心とする幼児教育によるところが大きい。知識より知恵を重視します。ユダヤ人は宗教を通じて徹底して道徳を教え込み、生きるためのノウハウを学び、疑問を持ち議論する習慣および週1回の休息日における家族との語らいの中で、強いメンタルと深い洞察力、思考力、交渉術などを身につけていきます。世界人口の約0.25%のユダヤ人、ノーベル賞の受賞率は20%ほどと異常な高さ(※40%とも言われています)。知れば知るほど、世界に散らばるユダヤ人の政治や経済への影響の大きさにも驚きます。
かつての日本にも四書五経の素読等「人づくり」を重視した教育がありました。しかし、明治以降の教育において人間教育は疎かにされ、もっぱら知識教育に偏っていきました。その結果、戦後まもなくはまだ余徳があったものの、知識はあっても人物的な深さのある人材が乏しくなったと指摘する声があります。新しいものや時代を創造する人物は、智慧や徳の学問、そういった教育の中から生まれるそうです。
どんな人材を育てられるかで、地域の将来が決まってくると思います。
秋田からビルゲイツのような起業家がたくさん誕生したら?!もし少子化が改善しなくても、少数精鋭の活力ある秋田の未来を考えられるなら、そんな悪いものでもないと思うのです。
いま、私には2歳の息子がいます。
人を育てる事は未来へつながる尊い仕事だと思います。
子供を通して未来を考えることができ、とてもワクワクして楽しいです。
将来を見据えて次世代の育成を上手にできたなら、それは自分自身の子供の有無に関係なく、地域全体が恩恵を受けることになります。
子供には無限の可能性があります。
世の中を明るくする、心の豊かな子供達がたくさん育って欲しいと願ってやみません。
人間は何のために生きているんですか?との問いに、アインシュタインは「他人のためです」と答えたといいます。
人を育てることは未来への大きな投資になります。
めぐりめぐって、その結果は、自分たちにも跳ね返ってきます。
未来を考え、育児に理解ある個人や企業がたくさん増えてくれると嬉しいです。
*********
(補足説明)
少子化対策も大切なのですが、そろそろ「量」だけでなく「質」の議論も必要だと思っています。
「量」だけ増えても、社会問題は解決しません。
将来に希望が持てなく、親の年金をあてにしたり(生活保護予備軍?)、心の病を抱えて障害年金を受給するような若者を益々増加させてしまっては、逆に若年層に対する社会保障費も増大し、社会全体での扶養者を増やすこともありえます。
経済は人口が増えさえすれば回復する(=税収も増える)というような単純なものではありません。
秋田でも若者の就職難や心の病は増加している問題です。
近隣アジアの成長が目覚しい中、日本の成長が鈍化しています。
「物づくり」で成長してきた日本ですが、「物づくり」は金融や商業にない成長の限界があり(買う人がいる、同じ品質のものを安く作るところがない、という条件を満たさないと駄目)、いまでは中国などの新興経済国にその優位を奪われつつあります。
歴史を学べば「世界の工場」であり続けた国はなく、また「工場」だけでは国として生き残れないとも言われています。
金融、IT、映画などの産業で、日本は優位に立てていません。
中国は香港を手に入れました。
東京は世界金融と商業の中心になり損ねました。
東京から撤退又は移転した外資系の金融業が香港に集中するようになりました。
しばらく世界における日本の地位は低下傾向が続くように思います。
よって、少子化が改善したとしても経済見通しは楽観視できないように思います。
現状を打開できるような人材育成が望まれるところだと思います。
「人づくり」には時間がかかります。
「量」も「質」も向上させられることが理想ですが、「量」の政策がかんばしくなく終わっても、「質」によりカバーされることは考えられます。しかしながら、「量」だけを求めた場合は、更なる社会問題が発生していることが懸念されます。
行政は時として、数値目標ばかりにとらわれることがありますが、数値を達成することが目的ではなく、問題を解決することが目的のはずです。
特に秋田は子供を増やしたところで、現状では育つと他県に流出していきます。
国際競争以前に、山形などに比べ国内競争において秋田は低迷しています。
企業誘致もいいですが、自立心や起業家精神を育てることで解決する問題もあると思います。
秋田の学力の高さは、教育現場の相当の努力があってのことだと思います。
それについては、とても素晴らしいことだと思っています。
しかしながら、依然として高い自殺率や、心の病の増加・・・
適切な時期に心の教育を手厚くすることで変わってくるのではないでしょうか?
(ユダヤ人は非行に走ったりニートになったりが少ないらしいです)
心を育てる教育は手間隙がかかると思います。当然、家庭の役割も大きく、親子の時間を確保するためにも、企業の両立支援などサポートは不可欠です。
子供を産めと言われても、そう簡単に産めるものではありません。
社会人になる前までの心を豊かにする教育のなかで、家族のよさを知り、家庭を作りたいと思う人が増えるようになれば、自然と少子化も改善の方向へ向かうかもしれません。
これからますます厳しい世の中になることが想像できるだけに、次の世代に何を残してあげられるかは、「人づくり」を重視した教育ではないかと思うのです。
物事、いろんな二面性があります。
勉強しろ!勉強しろ!の孔子に対して、学を絶てば憂いなし・・・と老子。古代の賢人、相反する思想が多々あるのですが、どちらも間違っていないと思います。
必ずしも儒教的思想だけでは人生を乗り切るのが難しい局面が生じることもあり、相反するような思想が必要なときもあります。答えは1つだけと思い込まない。
白か黒かでなく、白も黒も相反するようでいて併せ持ってバランスよく調和するという柔軟な考え方が、これからを生きていくためにはより必要になると思います。
ブータンかユダヤ・・・ではなく、ブータンもユダヤも、今後の秋田の在り方を考える上で参考になると思っています。
私自身、産後に原因不明の体調不良で苦しんでいても、息子が小さくて、赤ちゃん同伴での病院受診を断られて、病院に行きたくても行けない思いをしたり、いまも子供の病気等に備えて仕事の調整に苦労していたりします。
産後に体調不良に苦しむ人は結構います。ある程度大きい総合病院には、託児所を併設することができたなら、産後の不調に苦しむ母親も病院への受診がしやすくなるし、子供自身の病気の際にも病児保育可能となれば、働く女性にとって大変助かります。
高齢者にかける予算に比べて、あまりにも子供にかける予算が少ない。
ファミリー・サポート制度などありますが、頻繁に利用するにはやはり負担が大きいです。介護保険では1割の負担で各種サービスが受けられます。
1歳未満の幼児は過酷な世話が必要になります。いまは核家族化がすすんで、その負担が全部母親にくることも珍しくありません。自分自身も体調不良で苦しむ中、1歳未満限定で利用金額上限を設けてもいいので、介護保険と同程度の負担で、家事代行や一時預かりサービス等が利用できたなら、育児がもっとラクだったと思います。
生後1~2年の、あの過酷な育児の日々を思い出すと、2人目には躊躇するという声も聞かれます。
核家族化で頼る身内が身近におらず、夫は連日遅くまで残業が続いて、育児の負担が母親だけに集中していることも珍しくありません。
支援が必要なのは企業で働いている女性だけでないはずです。海外では日本以上に気軽にベビーシッター等を利用している国も多いです。
子育てを社会全体でなんとかしなければならない問題だと思ってくれているのなら、核家族化等を背景に介護保険制度ができたのと同じぐらい大きな政策、介護保険制度をあらため、「育児介護保険」制度を創設して、育児についても介護サービスと同じぐらいに多様なメニューを低価格で利用できるようになったらよいのにと思います。
自分自身の経験を通して、女性の仕事と育児の両立の難しさを身にしみて感じています。息子は1歳になる前から保育園に通園していますが、病気等で何日も連続して休むことが珍しくありません。もし自分が雇用される立場で、何日も連続して早退したり欠勤しなければならないとなったら、どこまで経営者は寛大でいられるでしょう? 周りを見ても、比較的実家の支援を受けられている人は仕事との両立が出来ていたりするけど、そうじゃない人は、旦那さんが協力できる体制だったり、ある程度の規模の会社で休んでも他の人が仕事をフォローできる状況があったりと、いくつかの好条件が整っている人でない限りは、かなり厳しい感じがします。
働く女性にとって、子供が病気をしたときのサポート体制があるかどうかは、仕事を継続していく上で大きいです。医療費の無料拡大よりも病児保育体制の充実のほうを切に願います。
「チャレンジド」という言葉があります。
~「障害をもった人」のこと。近年、アメリカで「ハンディキャップド」に代わって用いられるようになっている。神様からチャレンジという使命を与えられた人、試練に挑戦する使命を与えられた人という意味である。すべての人間は、生まれながらに自分の課題に向き合う力が与えられている。しかも、その課題が大きければ大きいほど、向き合う力もたくさん与えられている、という考え方に基づいて作られた新語である。障害をマイナスとして捉えるのではなく、障害をもつ故に体験するさまざまな事象を自分自身のため、あるいは社会のためにポジティブに生かしていこうという意味合いである。総理大臣の鳩山由紀夫が2009年10月の臨時国会における所信表明演説の中で、このことばを用いてから注目されるようになった~Yahoo!辞書より
多くの子供たちは障害者ではありませんが、これからの日本の状況を考えると、生まれながらに高度成長期を過ごした人とは違った重い課題を背負うことが想像され、試練に挑戦する使命を与えられているように思います。
仕事と家庭の両立支援は、非常に大切な取り組みです。より多くの企業に理解をしていただき、育児を応援していただきたいと思っています。
それと同時に、「量」だけでなく、「質」の向上にも同じぐらいチカラを入れて取り組んでいただきたいと、願っております。
****
更に補足説明
思想が絡むと、筍のように次々と、いろいろな意見や反対を言う人が出てきますので、現在の日本では、国や行政が主体となって、幼少期に人間としての土台作りの教育に力をいれるのは限界があり難しいだろうなぁ~と思っております。
それだけに、学校だけに任せるのではなく、家庭による子供の育て方が大事と思います。(3つ心、6つ躾・・・の、江戸時代の子育てに学ぶべし)
歴史を学べば「世界の工場」であり続けた国はなく、また「工場」だけでは国として生き残れない・・・という話のあたりは、石角 完爾氏のサイトを参考にさせていただきました。
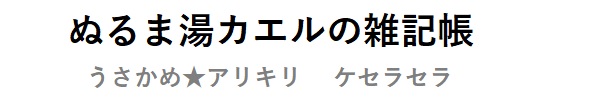
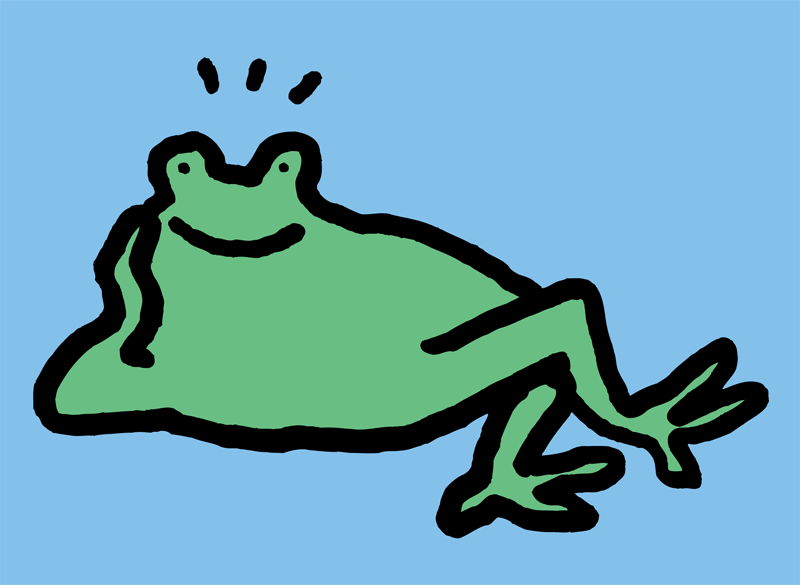

コメント